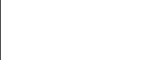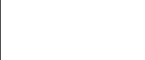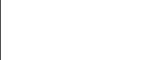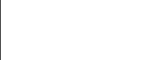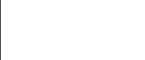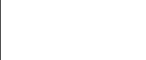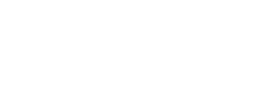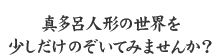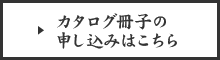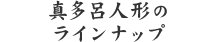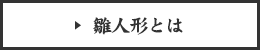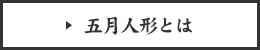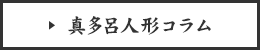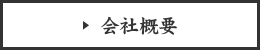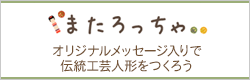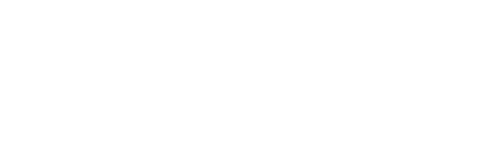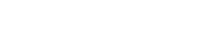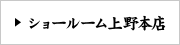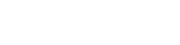真多呂人形のブログ記事一覧(雛人形)
真多呂人形のブログ詳細ページです。真多呂人形では定期的にブログを更新しており、伝統的な木目込み人形の知識やショールームのイベント情報、毎年の世相を表した変わり雛の発表など、さまざまな内容を掲載しています。ブログ内容に関する皆様のコメントもお待ちしております。
- 雛人形の後ろに立てられている金屏風に込められた意味
-

- 金屏風に込められた意味 雛人形の後ろに立てられている金屏風は、今でも披露宴の高砂の背景や、 芸能人の婚約・結婚記
- 最古の座り雛・室町雛について
-

- 大人が楽しむ室町雛について 雛祭りは、元々は端午の節句の祭りで、その発祥は中国だと言われています。 元々は、お祓
- 今も山形などにみられる寛永雛とは?
-

- 寛永雛と山形の雛人形の関係は 江戸時代初期の17世紀前半に誕生した寛永雛は、 男雛は12センチメートル、女雛は9
- 今も佐賀などにみられる次郎左衛門雛とは?
-

- 佐賀の文化遺産である次郎左衛門雛 次郎左衛門雛は、江戸時代に雛屋次郎左衛門という人形師によって、 京都にて創設さ
- 今も京都などでみられる享保雛の特徴とは?
-

- 享保雛(きょうほびな)の歴史 享保雛(きょうほびな)は、江戸時代の中頃である1716年から1736年頃の享保年間に
- 今も大分などにみられる古今雛の特徴とは?
-

- 大分県のひなまつりにも見られる古今雛とは? 大分県の玄関口として知られている中津は、 一万円札でも有名な福澤諭吉
- 今も薩摩のひなまつりなどにみられる有職雛の特徴とは?
-

- 有職雛(ゆうそくびな)の特徴とは? 有職雛(ゆうそくびな)は、京都の宮廷の文化を受け継ぐ正統派の雛人形のことで、
- 雛祭りとはまぐりの関係
-

- 雛祭りにはまぐりのお吸い物を食べる理由 雛祭りには今でも、はまぐりのお吸い物を食べますが、 それにはいくつかの理
- 押し絵のくくり雛とは?
-

- 奥州に伝わる「くくり雛」のルーツと歴史 岩手県奥州市水沢区には、くくり雛と呼ばれる伝統的な雛人形があります。 押
- 無形民俗文化財のもちがせ流しびなとは?
-

- 厄除けと身代わり信仰の風習が生んだ流しびな 日本のひなまつりのルーツは、平安時代までさかのぼります。 現在のよう